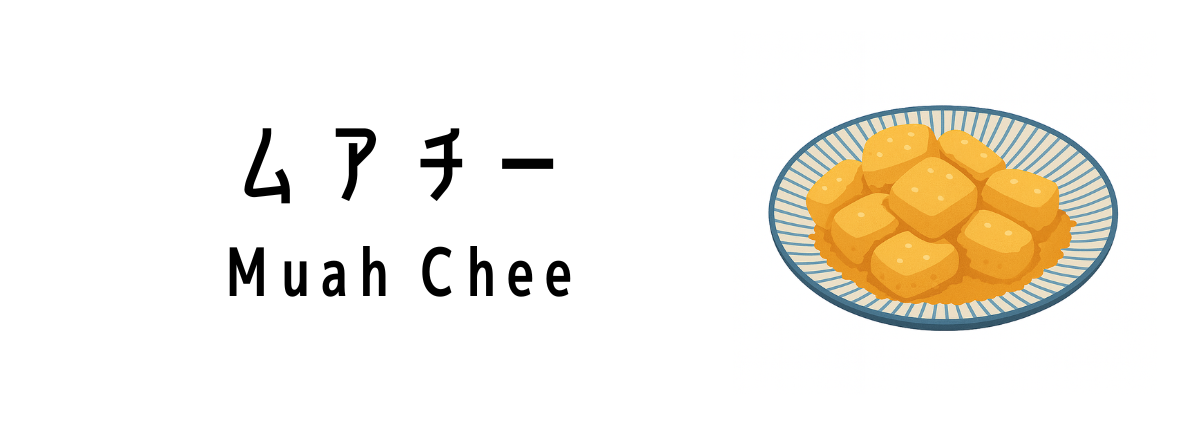
ムアチー(Muah Chee)とは?
ムアチー(Muah Chee)は、もち米粉を蒸した生地を小さくちぎり、炒りピーナッツと砂糖を混ぜた粉をまぶした伝統的なおやつで、日本のお餅に似ていますが、柔らかく弾力がありながらも軽い食感が特徴です。シンガポールでは中華系コミュニティで親しまれていて、ホーカーセンターやフードコートなどで稀に見かけます。日本人としては「ピーナッツパウダーを使った小ぶりのきな粉餅」を想像するとイメージしやすいです。

最近のムアチーについて
近年のムアチーは、従来のピーナッツだけでなく、抹茶、黒ごま、ココナッツ、さらにはカラフルなスプリンクルやチョコレートソースを使ったバリエーションも登場しています。伝統菓子に現代的な工夫を加えたモダンなスイーツとして若い世代にも人気です。
日本の餅との違い
ムアチーはもち米粉を蒸して作り、仕上げにピーナッツと砂糖をまぶすのが特徴です。生地は柔らかく軽い口当たりで、蒸した生地をちぎって食べるのが特徴的です。一方、日本の餅はもち米を蒸して搗き固めるため、弾力が強く噛み応えがあるのが特徴です。また、日本の餅は焼いたり煮たりして調理法の幅が広く、砂糖やピーナッツではなく醤油やきな粉など多様な味付けで食べられます。
実際の食べ方としては、ムアチーは「軽くて甘いスナック」、日本の餅は「食事や保存食にもなる主食寄りの食品」のような位置づけになっています。
日本の「餅(もち)」名前が似ている理由
ムアチーと餅(もち)の名前(音)が似ている理由ですが、結論から言うと偶然となります。ただし、ムアチーと餅は語源的に共通のルーツも持っている関係でもあります。
ムアチーは、福建語(ホッケン語/閩南語)の「麻糍(muâ-chî)」に由来しています。「麻」はゴマや穀物をまぶす意味、「糍」はもち米で作った食べ物を指します。この「糍(チー/ci)」が、日本語の「餅(もち)」と同じく中国語起源の言葉で、どちらも「もち米を加工した食品」を意味しています。そのため、語源的には「もち米=餅(糍)」という共通のルーツを持っています。
一方で「ムア(muah)」と「モ(mo)」が似ているのは、言語的な必然性はなく、偶然に近い響きの一致となります。Muah Cheeの「Muah(麻)」は福建語での「ごま」を意味し、餅の「Mo」は日本語の音読み(中国語の「餅:bing/もち米の菓子」)が転訛して日本語になったものです。つまり、語源的に「Muah」と「Mo」は別物で、似て聞こえるのは偶然となります。
シンガポールでMuah Cheeが食べられる場所
ムアチーは、ホーカーセンターやコピティアム、パサマラなどで販売されています。その他では、旧正月や中秋節、地域のイベントなどでも出店が登場します。特にチャイナタウンやゲイラン、郊外の住宅街ホーカーなどでより見かけることが多い印象です。ただし、ホーカーセンターやフードコートの定番フードというわけではないので「タイミングがあれば食べる」といった食べ物でもあります。


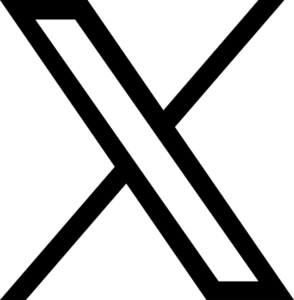





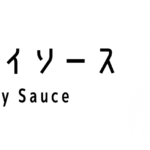
ってどんな花?-300x169.jpg)

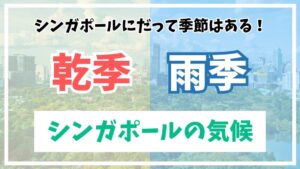
2-300x169.jpg)
